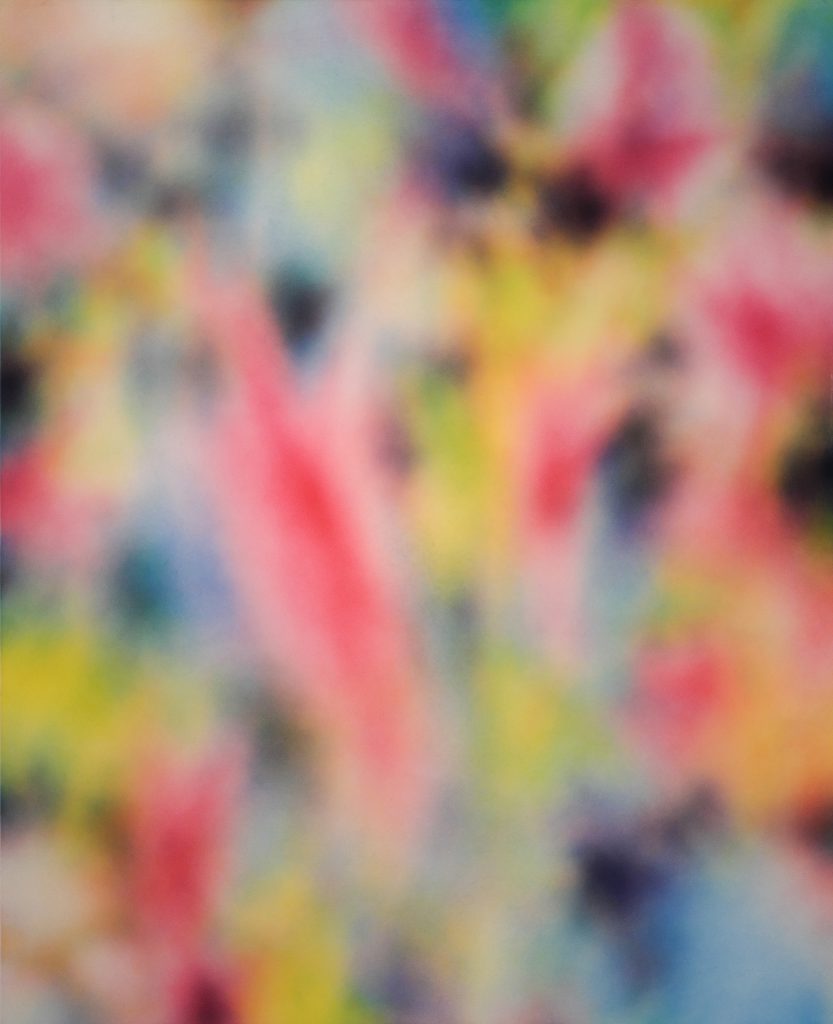ー 物たちの外部へも精神へも通じていない一本の大道沿い、詩篇によって形づくられる活字の茂みにおいて、ある種の果実たちは、一滴のインクにみたされる球体の一聚合から出来ている。ー 桑の実 / フランシス・ポンジュ「物の味方」より / 阿部良雄訳
- Aux buissons typographiques constitues par le poeme sur une route qui ne mene hors des choses ni a l’esprit, certains fruits sont formes d’une agglomeration de spheres qu’une goutte d’encre remplit. -
ポンジュ(Francis Ponge 1899~1988)(物の味方 1942)の唯物論は、実存的印象というより現在では反デジタルの世界把握として読む事ができる。あるいはまた、ポジフィルムの光は、デジタル写真の格子(画素)に囚われ抑圧的に収納された光よりも、輝きとその拡散の豊かさがデジタルをはるかに凌駕していることは、手元のプロジェクターの細い光の中でも、多分幼子の瞳でも、その違いを視認できる。単なるテクスチャー(材料の表面の視覚的な色や明るさの均質さ、触覚的な比力の強弱を感じる凹凸といった部分的変化を、全体的にとらえた特徴、材質感覚、効果を指す。-wiki)の表情と受け止めるだけでは、現在の絵画表出との出会いの経験を軀に刻む事はできない。絵画アナログが海馬に与える経験情報は、観念的な認識というレヴェルでは処理することはできない。近寄りあるいは離れつつあるいは瞼を閉じて暫し眠りさえ挟んだ後に、平面のイリュージョンに意識が吸収される目眩に浮遊する(実際にそうした経験を口にした観覧者がいた)。対峙経験を繰り返すことで、画家の固有な取り組みの個人的だった行方をふいにわれわれは共有して、振り返れば*クァンタムミストへ微分分解した意識の中を高らかに彷徨っている。
プリベンション(宇佐美圭司 1940~2012)をサブタイトルに置いたナガノオルタナティブ2017 徳永雅之展では、30年近くに渡るひとりの画家の歩みを見渡すことのできる作品群によって、画家の行ってきた仕事の時間を経験する空間がうまれた。エアコンプレッサー(空気圧縮機)でカラーミスト(霧)を平面画面に投射噴霧する「距離の推し量り」をメソドとし、例えばスイスのイエロー(Yello / http://yello.com)が、音そのものを反響する空間から真空パックするかにクリアに取り出す手法に似て、アウトフォーカス(無焦点)のクァンタムミストを朧なまま量塊として粒子を加算定着させる世界関与(減法はない)を平面作品化している。
「ー内なる他者性を排除しかねないさまざまな原理主義者の台頭や、外部の他者の捏造することによるアイデンティティの主張が横行する時代への、冷静な批判を秘めたものであるともいえるだろう。そう、曖昧さとは、他者性を許容する場所に踏み留まろうとする意思なのだ。ー」
画家が参画出品した1998年「曖昧なる世界ー影像としてのアート」展カタログ冒頭、建畠晢(1947~)は「曖昧さについて」という一文の最後で、曖昧茫漠な表出に傾いた選出作家作品に対して、やや予言的にその朧さに立って行けと示しているが、20年近く経過した現在、曖昧さの可能性の中心よりも、別の深層にシフトした領域に作品は位置していることが、間近までにじり寄った作品のクローズアップで視えてくる。レオナルドの人間の尺図でも解る、人間の意識投射の行為空間を切り開くのは、時に筆であり、この画家の場合エアコンプレッサーとノズルである。これをナイフを持った狩人と鞭を手にしたカウボーイとして相対すると、空気圧の強弱で対象との距離を測る唯物的な霧が、定着画面手前で噴霧現出されていることが判る。つまり噴霧の状態という空間が画家のアプローチの世界をプレイベント化する。これはポロックのドロッピングの放下空間(重力+加速+他)とも似ている。この時既に画家は世界の狭間という他者性の介入を許しているわけだ。絶対的にはコントロールできないノズルという仕組みに画家は「自由」を見出しているのだとも言える。この装置の態度が建畠の「冷静な批判」と結ばれる。噴霧マスキングした小さな紙の画面に同じ手法で制作されたエスキス作品群があり、これには画家がアントマンであったかと驚かされる。
エンジンキャブレターもそうだが、インクジェット出力は、このミスト系のデジタル版であり、家庭用プリンターから業務用のかなり大型のものもある。フィルム差異にて前述したように、色彩液体がノズルからミスト状に噴霧されるアナログの、所謂粒子層への介入という人間の手の仕草は、デジタルインクジェットの格子情報の併置命令とは全く異なった、介入道程(プログレス)が画面に遺されている。ベンチェリ(Giovanni Battista Venturi 1746~1822)よりも以前に、多分唇をすぼめてぷーと水を吹き出し虹を顕すようなことを人間は遠い過去からしてきたに違いないと思うが、「霧のいけうち®」の開発特許など現在では、数μm〜十数μmの霧を散布することが容易に出来るようで、生活の馴染みの深い障子張りやアイロンがけの他にも、加湿器など脇に置かれる生活がある。噴霧するノズルによって、JR九州が運行する特急「指宿のたまて箱」ではドアが開いた際にミストを噴射する演出を行っている。
産業サポート的な「噴霧のシステム化」と、画家の行う「意識のクァンタムミスト」の具現化は、言うなれば凡庸な道具を使って照らす行方が大きく異なっている。画家の意識のミストは、人間の知的知覚の拡張に向けられており、目覚める前に喪失する儚い光景として、あるいは記憶に仕舞われた一瞬として、あるいはいつかきっと精神だけとなって宇宙を高速ですすむ視界となって、今ただ其処に在る。
文責 町田哲也
*作家自身は、この色粒子のボリュームを「霧」ではなく「光」としている。個人的に霧が多い地域で過ごしているせいもあり、画家の手元のノズルや霧吹きへ妄想をスライドさせてていくうちに、霧状の量子的意識を勝手に浮かべてしまった。腕を伸ばせばこちらも霧と同化して偏在するかのイメージに任せた。